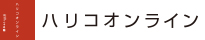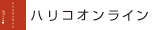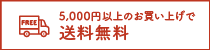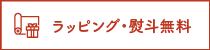干支とご一緒にいかが?節句にも飾れる張り子
もう10月も終わりますね。今月から年末に向けて辰張子の出荷が本格化して、在庫が一気に減る事が増えてきました。ハリコオンラインでも何点かの商品が在庫切れになってしまい、買えなかったお客様には誠に申し訳なく思います。在庫切れ商品ですが、まだまだ入荷予定ございますので、お待ち頂けると幸いです。
ここ最近は干支商品が半数以上を占めておりますが、干支張子と共に「五月人形」もお買い上げ頂くお客様もいらっしゃいます。早めにご購入頂いているか、初正月向けでしょうか?
 端午の節句前の時期と比べ、今の時期は比較的小ぶりな商品が売れているかなという印象です。手のひらサイズの「豆寅」や「ミニ五月人形 トラ」、「豆でんでん付 こいのぼり(紙音)」、絵本つきの読み聞かせ絵本と張り子「こいのぼり」「黒の鯉と金の鯉」などです。
端午の節句前の時期と比べ、今の時期は比較的小ぶりな商品が売れているかなという印象です。手のひらサイズの「豆寅」や「ミニ五月人形 トラ」、「豆でんでん付 こいのぼり(紙音)」、絵本つきの読み聞かせ絵本と張り子「こいのぼり」「黒の鯉と金の鯉」などです。

左が「絵本つきの読み聞かせ絵本こいのぼり」みぎが「実り鯉のぼり」
より鯉のぼり的なものですと「実りこいのぼり」「雲とこいのぼり」をお買い上げ頂くお客様も多いです。こちらもハリコオンライン内のこいのぼりの中ではコンパクトめで、デザインも現代的なものになっています。

干支にも五月人形にもいかがですか?
辰の破魔矢

破魔矢辰と五月人形をおいたイメージ
五月人形としては破魔矢・破魔弓の商品が現状ラインナップにないのですが・・・。干支の破魔矢辰はいかがでしょうか? 鯉のぼりといえば、激しい滝を登りきった鯉が龍となる故事「登竜門」が元になっています。干支飾りだけでなく五月人形として飾るのもいいかもしれませんね。
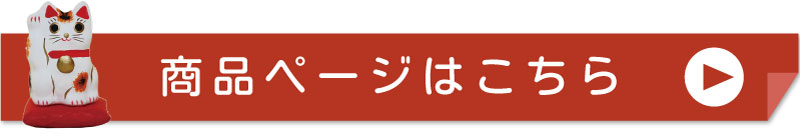
ひな祭り系はないの・・・?
ひな人形は「3月3日までに仕舞わないと、お嫁に行けなくなる」というジンクスがあることから飾る時期が五月人形よりシビアなため、残念ながら開発できていないのが現状です。 とはいえ、ハリコオンライン内でも「ひな祭りにあう」商品もございます。菱積み金魚
実は3月3日は「金魚の日」というのをご存知でしょうか?江戸時代では雛人形と共に金魚鉢を飾る習慣がありました。 諸説あるようですが、はまぐりやスルメなど水に関する物が供えられていたので、水に関連する物として飾られていたのではと考えられています。 また、平安時代頃は子供の身代わりに厄を受けるよう願い川に流していました。
菱積み金魚のイメージ画像
「菱積み金魚」の「菱型」は「子孫繁栄」や「無病息災」の吉祥紋様として親しまれていた菱紋を木で組み、縁起が「積み重なる」よう願いを込めたモチーフです。
また、金魚は中国語で「金余」と同じ発音ということから、金運アップの縁起物とされています。
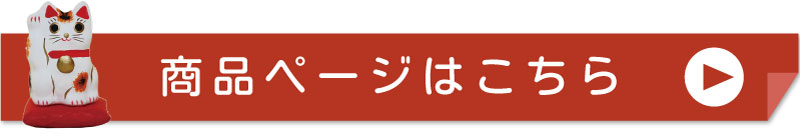
だるまうさぎ
うさぎが可愛いだるまになりました。まん丸な体は手毬を思わせる愛らしさに仕上げています。明るい色合いは、お祝いや春先の雰囲気にもマッチするかと思います。 ウサギは昔から縁起の良い生き物とされています。また、海外でも縁起の良い生き物として扱う国が多いです。日本でのウサギは「子孫繁栄・安産」、「縁結び」「厄除け」などのご利益があるとされています。
【子孫繁栄・安産】
うさぎは繁殖能力が高く多産であることからご利益があるとされています。
【縁結び】
古事記の「因幡の白うさぎ」神話では、白うさぎが「大国主命(おおくにぬしのみこと)」と「八上姫(やがみひめ)」との結婚を予言したことが由来とされています。
【厄除け】
「兎」の字が「免」の字に似ていること、足の速さから「災いを逃れる」と言われています。

だるまウサギひな祭りイメージ
だるま人形ですので、雛人形のように「仕舞うのが遅くなると・・・」のジンクスも気にせず、飾り方を変えれば年中飾りとして使用できるでしょう。
また、3月といえばひな祭りのほかにイースターもあり、大活躍するかと思います。
初正月って何?
記事の冒頭で、「初正月向け?」と予想していましたが、ここで「初正月」を初めて知った方に初正月について解説いたします。
初正月は、生まれて初めて迎えるお正月のこと。日本は昭和24年以前まで、お正月にみな一斉に歳をとる「数え歳」の制度をとっていました。生まれて初めてのお誕生日にあたるため、特別なお祝いをしていたようでした。
昭和6年出版の「国民礼法」(熊谷正雄 著/小笠原流国民礼法刊行会 出版)の中で「初正月」について、このように記していました。
男の初正月には弓矢を床に飾り鏡餅酒するめ昆布尾鰭附魚を供えて祝う これは古武士の式にて弓は武士の表道具の一である。 女の正月には羽子板を床に飾り鏡餅するめ酒昆布鰭の魚を供えて祝う これは羽子板は日本婦人の古からの遊具で男子の凧を上ぐると同じく春の青空を仰向き遊ふ道具である。
さらに、日本民俗学者の創始者である柳田國男の「産育俗語彙」(1935年発刊)のうち「初節供」の章では、地域ごとの特色ある行事とその呼び名をまとめています。節句についてなので、時期が違うものもありますが、初正月に贈り物をする地域にも触れています。特別な料理を作る地域もあれば、贈り物をする地域とがあるようです。
・「オハツイハヒ」上野(群馬県)多野郡。男児には破魔矢。女児には羽子板。
・「ハンキハユミ」肥後(熊本県)上益城郡。男児には破魔矢や破魔旗。女児には羽子板。
弓や矢の飾りは端午の節句でも共通する飾りですよね。 また、羽子板といえばお正月の遊びとしても馴染み深いですよね。厄除けの飾りとしても贈られていたようです。
少し時期はずれますが、備後(広島東部)の沼隈郡は男児の初年の暮のうちに武者を飾りつける習慣がありました。柳田國男によると「ハンキ」「破魔」と関係があると見ているようです。
また、お正月の飾りでお馴染みの「柳もち」。長門(山口県)大津郡宇津賀では、娘の初正月に飾って、3月3日まで保存していたとか。
このほか、初正月のお祝いで料理を作る地域では、近隣や近所に振る舞うものが多いようでした。昔の日本にあった、親族の繋がりの濃さや「地域で子育てをする」感じが伺えますね。 情報や流通が劇的に発達した現代では、地域の特色が薄くなっているように感じます。また、こうして調べてみると、地域差のある習慣がもっとあったのかもしれないなと思います。自分の住む街のかつてあった特色など、もっと知っていきたいなと思う機会となりました。